インタビュー「ピアノとわたし」(18)
三浦広彦さん
プロフィール
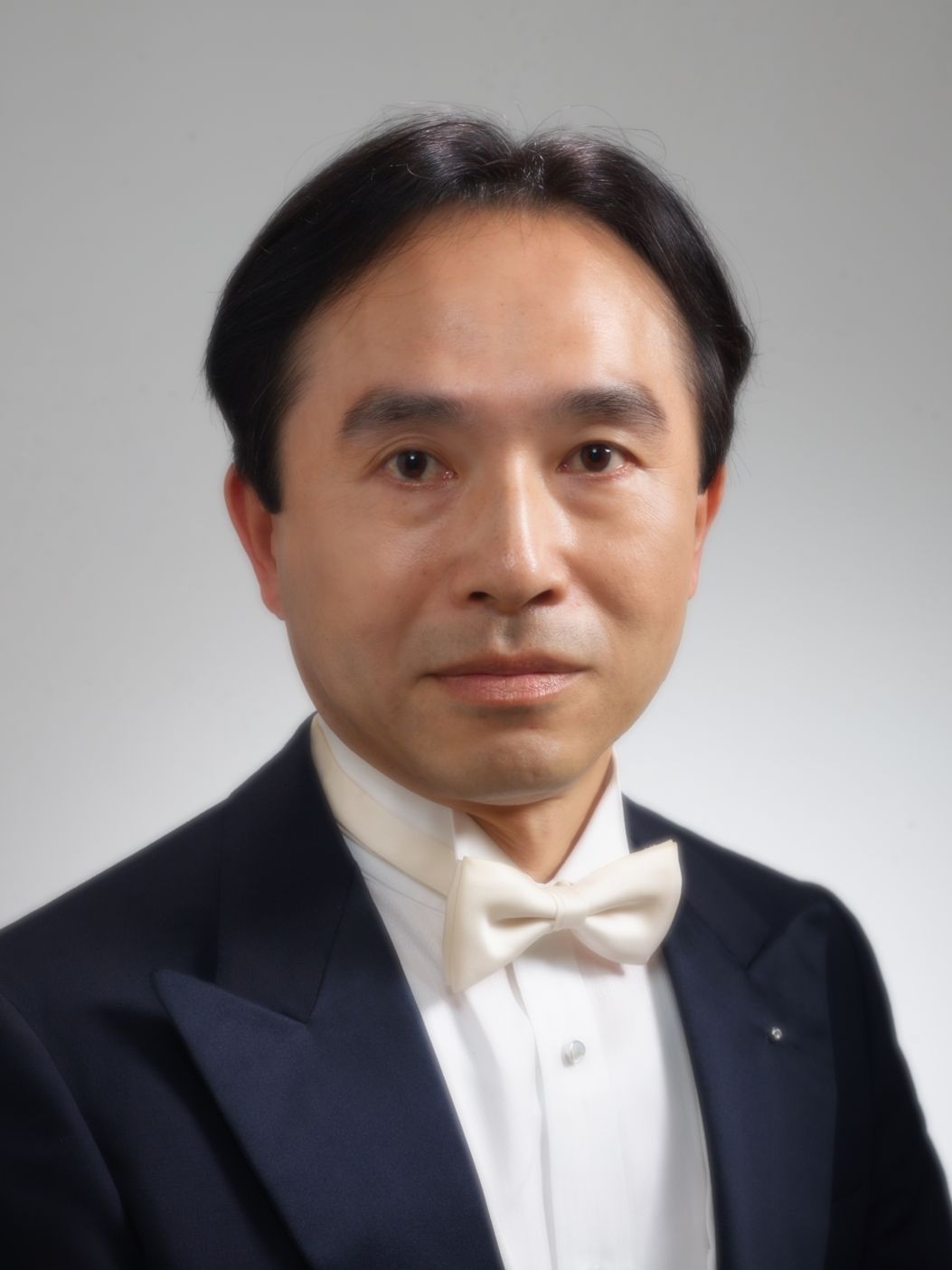
1963年、福岡市生まれ。福岡大学理学部卒業。河合楽器製作所ピアノ事業部Shigeru Kawaiピアノ研究所主監。テノール歌手の御尊父とピアノで共演されたリサイタルを収録したCDをリリース。
インタビュー
―ピアノ研メンバーでの河合楽器製作所竜洋工場見学の際はお世話になりました。また、11月11日の「静岡大学 ピアノとウェルビーイング研究所設立記念シンポジウム」では「静岡県のピアノ産業とピアノの未来」の座談会にご登壇くださいまして、ありがとうございました。三浦様が10月にご自宅にSK-5を入れられたとのことで、今日は、ご自宅音楽室にてお話を伺わせていただきます。こちらのポスターは、お父様と共演なさった時のものですか?

お父様と共演されたリサイタルのポスター
はいそうです。1998年のものです。父は、テノール歌手でして、福岡教育大学で教鞭を執っていました。母はピアノの教師です。父は家でも歌を教えていましたから、常にピアノは家に2台。一時期は2台ピアノの演奏ができるようにということで、合計3台置いてあったこともありました。ヤマハとカワイのピアノが両方ありまして、セールスマンや調律師も両社から出入りしていましたので、子供の頃からそういう人たちを観察していました。生まれた時から、ピアノ業界の中にいたような感じですね。
家でも常に音楽が溢れていますので、3歳くらいから何か聞きかじると、それをピアノで弾いてみる、というようなことをしていました。小学生の間だけは、父の同僚の男性ピアニストのお宅に通ってピアノレッスンを受けていました。しかしピアノの練習はあまり好きではなかったですね。私は聞き覚えで弾いたりするのは得意だったんですが、それをその先生は嫌ったんですね。ちゃんと読譜力をつけなきゃと言って、簡単に覚えられないような曲をわざと与えたんです。それで、当時としてはちょっと珍しくバルトークの《ミクロコスモス》とか、そんな曲を割と最初から与えられて、それでますますレッスンは嫌いになったんです。でもレコードやテレビによって耳から入って素敵な曲だな、と思えば、自然と音がわかってくる。練習を真面目にするというより、そういうのが好きでした。
父は福岡でオペラ団体を立ち上げたんです。昭和36年のことです。そんな時代に地方でオペラやるというのは、非常に珍しいことでした。お金がない中でも、定期的に公演をやっていて、昭和40年代になると、イタリアもののいわゆるグランド・オペラと言われるような本格的なものを日本語で上演するというスタイルでやっていたんです。私が5歳の時に、初めて福岡で《蝶々夫人》を上演することになりました。そうすると子役が必要になりました。私が考えるところその子役の条件は「長時間の練習におとなしく付き合える」ということ、「なるべく体重の軽い子」ということ。主役のソプラノ歌手は、子供を抱いたまま歌ったりもするわけなんです。体重は軽い方がいいし、できれば男の子がいい、というのもあって、そうすると私が適任だったわけです。ですから、私のデビューは大きな大きな舞台。《蝶々夫人》の子役なんです。福岡だけではなく、広島にまで遠征公演しています。父は広島大学教育学部を出て中学教師になり、それから東京芸大の声楽科に入ったんです。広島でお世話になった人たちとの公演ではその頃、NHKのニューイヤー・オペラコンサートの常連だった曽我栄子さんが《蝶々夫人》で、うちの父がピンカートンをやりました。

1970年、《蝶々夫人》の広島公演で子役を演ずる三浦さん
その他にもあと、《カルメン》とか《カヴァレリア・ルスティカーナ》とか《ラ・ボエーム》などにも子役として出演しました。オペラに出るっていうことは、練習からずっと付き合うわけですね。そうすると、2時間、3時間と長いオペラもほぼ全部暗譜してしまうわけですよ。ですから、オペラが子守唄みたいなものなんです。
―そうですか、なるほど。
それが今でもすごく懐かしい音楽になっているんです。特にプッチーニの音楽が。それで、大学生くらいになった時に、ピアノでオペラを辿って弾いてみると、すごく自分でも気持ちが良かったんですね。
―この間の7月に、東京初台の新国立劇場で《ラ・ボエーム》を初めて観てきました。
あの、オペラの中に、一声子供のソロがあるんですよ。第二幕の雑踏の中でのおもちゃ屋さん登場の場面です。「太鼓とお馬が欲しい」という歌詞でした。それを小学校3年生の時にやりました。歌はそんなに本格的にやってはいませんけれども。まあ、そういうオペラの幼児体験をピアノで再現するっていうのが一番のピアノの楽しみ方となりました。
また高校生の終わり頃だったんですが、母親が用意してくれたアルゲリッチのレコードがすっかり気に入りました。「英雄ポロネーズ」がかっこいいなと思ったわけですよ。それで、アルゲリッチのほか、ルービンシュタインとか、ホロヴィッツとか、中村紘子とか、ポリーニとかと聴き比べたんですが、とにかく自分には衝撃的な、すごくスマートな、しかもバランスのいい演奏と思ったのはアルゲリッチなんです。アルゲリッチの《子供の情景》も素晴らしい。結局、その『子供の情景』がアルゲリッチのソロアルバム最後のスタジオ録音になっているんですよね。とにかく、アルゲリッチとの出会いで、ピアノというものに目覚めたという感じでした。
―ご両親はどんなふうな感じでいらっしゃったのでしょうか。音楽家になってほしい、という思いも持っていらっしゃったのでしょうか?
音楽家にしたい、みたいなことを強いられなかったのが良かったんじゃないかと思うんです。まあ、家は常に音楽に満たされていたんです。あと、イタリア・オペラが来日ということになったら、東京まで家族でそういうのを聴きに行くんです。父は研究・仕事としていくわけですが、母も私もついていくわけです。当時は、学校休んでそんなとこ行っていいのかな、って思っていましたけれど、今思うと本当にいい経験をさせてもらったなと思っています。
―ピアノのレッスン通いは小学生までで、中学校の頃は、全くもうピアノは弾かれなかったのですか?
弾かなかったですね。
―そうなんですか。
あと、私のもう一つの関心が相撲なんですよ。大相撲とプロ野球は福岡って両方通える環境にありまして、私は毎年大相撲九州場所に入り浸っていました。そして、各部屋の稽古場に毎週日曜日の朝、通うわけです。で、最初から最後までずっといるわけですよね。それで、関取からも認められてスカウトが来てしまいました。
―え?
力士にじゃなくてね、行司になりなさい、ってね。行司の仕事には、番付の文字を書く仕事も、場内アナウンスする仕事もあるんです。相撲の文字は、空席ができないように、という思いから、なるべく黒い部分を多くして書く独特の書体です。そんなわけで、就職先として私が考えたのは日本相撲協会と河合楽器だけなんですよ。
―その組み合わせには驚いてしまいます。相撲にハマったのはどういうきっかけなんでしょうか。
家の前が本場所の会場であったということもあるし、まあ、元々好きだったんです。今でも大相撲はしょっちゅう見に行きますし、最近は、ピアノだけではなくて、大相撲に関しての講演もたまに頼まれたりするんですよ。
―そういえば、吉田秀和が、相撲についても書いていますね。
オペラとか歌舞伎とか相撲とかっていうと、まあ同じようなもんじゃないかと思います。そうやって、一つの型がある中で創造性がある、というのがいいんですね。相撲に通いながらピアノを弾き、ピアノが本当に好きになったのは、高校生の後半くらいですね。アルゲリッチのレコードとの出会いのタイミングですね。大学は数学科に進みまして、就職先も何かピアノに関わったことにしようと思って、最初は調律師くらいしか思い浮かばなかったので、ヤマハの調律師学校を受験する直前まで行ったんですよ。それが、大学4年生の秋の話で、そのタイミングで、父が親しかったカワイの福岡の営業の方が、ピアノの研究開発の職場に入るのがいいのじゃないかと言ってくれて。それで、カワイの技術職というところで入社試験を受けたんですね。その頃は本当に就職が楽な時代でしたから、「なんとしてでもピアノの開発部門を希望します」って強く言ってその希望が通りました。14年くらいそこにいたんですが、2005年に、お客様相談室っていう窓口がカワイにもできて、その創設メンバーに指名されて、顧客対応の仕事に従事するようになりました。研究開発部門とはかなり違う仕事です。研究開発部門では学生時代の延長のような部分もありましたが、お客様相談室に移って、社会人としての勉強をさせていただいたと思っています。
研究所にいた頃はですね、毎日、ピアノに囲まれて、朝一番に起きて一番に工場に入って、そこで可能な限り、その場を占有して始業前にフルコンを1時間くらい弾くということをしていました。小型のグランドピアノを扱っていた感覚とはやっぱり違います。仕事を始めて、最初は寮生活でした。そこには自由に弾けるピアノはなかったので工場に行って弾くというわけです。そういうことを好ましく見る人ばかりじゃないですよ。「ピアノの練習に来ているわけじゃないだろう、お前は」ってそんなふうに考えている人もいます。でも、まあそれをやり通したんですね。他にピアノを狙っている人もいますよ。当然ライバルもいたんですけれど、やっぱりそこは根性で、会社を休む日以外は、一番に行って弾くぞ、と思っていました。フルコンが静かなところで弾けるというのが、本当に練習環境として最高なんです。研究室からお客様窓口に移った時は、フルコンが弾けなくなってしまいましたから辛かったですね。今度は逆に、5時に仕事を終えたら、もうなるべくすぐに家に帰って、夜の時間に練習しました。時間内に仕事を終えるように、必死でやりました。
ピアノのソリストではアルゲリッチ、そして、声楽伴奏ではスミ・ジョーなどと共演しているヴィンチェンツォ・スカレーラが私の理想となりました。スカレーラの演奏を真似てやっておりましたら、歌曲伴奏を次々頼まれるようになったんです。県内での舞台が中心でしたが、本番の数がちょっと多すぎて、もう実力以上にどんどん広がっちゃったんです。30代から40代にかけてのことです。それで追い込まれて、ジストニアを発症したのではないかとも思うのです。そして段々と弾けなくなっていたんですね。私は、ジストニアを発症する多くのプロの方のように長時間基礎練習みたいなことをやってきたわけではないですが、実力以上の依頼を抱え込んでしまったことで、脳神経にストレスがかかったんだと思います。声楽伴奏の依頼が色々来るようになってから、父との共演の話になっていったわけですが、父が声楽家だからこうした、じゃなくて、息子がいつの間にか伴奏ピアニストになったから、じゃあ共演やるか、ということになったわけです。今思うと、その演奏会あたりから、手の不調が始まったんです。
―そうでしたか、それは辛いことですね。カワイの工場でフルコンを弾いていらっしゃった頃は、どんな曲を弾いていらっしゃったのですか?
アルゲリッチの真似で、一番自分にしっくりしたのはシューマンです。《子供の情景》とか《クライスレリアーナ》などをよく弾いていました。
動画:シューマン《子供の情景》より「見知らぬ国」を弾く三浦さん
シューマンが一番自分にはぴったりしているんだけれども、シューマンもどうやらジストニアだったらしい、というのは何とも不穏な符合です。研究によれば、ジストニアを発症するのは多くが生真面目な男性なんだそうです。女性の発症は少ないです。多分、ジストニアという症名に行きつかずに、なんだか変だと思っている人はたくさんいると思います。
最初おかしいな、と思ったのは父との共演の本番で、なぜか、指が丸まっちゃったんですね。それが、どんどん顕著になっていって。本当に一番好きなことができなくなるっていう恐怖と焦りが押し寄せてきました。
―お医者には行かれましたか?
もう行きまくりました。最初は、整形外科に、それもどこがいいかなんて分かりませんからあちこちに。神経内科が本当は通うべきところなんですが、それを知るまでに10年かかっています。本当に、精神状態もおかしくなりました。食べられない、眠れない、で。今から10年ほど前に2年間会社を休職しているんですよ。

ジストニア治療の様子
―それはお辛かったですね。
絶望的だけれども、まあピアノを弾き続けたんですね。あるとき、転機がありました。治そうとして、いろんな病院巡りしていたんですが、それをやめようと思ったわけですよ。これをやっても時間の無駄だと。まあ、平均して、全体的にざっといって7本指くらいで弾いている感じなんですね。左手は薬指と小指に問題があり、右手は中指に問題が出る。もう、それはしょうがないと。その状態でできる範囲のことをやろうという考えに変えたら、意外となんとかできるようになってきたんです。声楽の伴奏の世界だからということもあるのですが、「7本指奏法」で以前よりも音を大切に扱えるようになった気がしています。どんな簡単な曲でも楽には弾けません。ピアノを弾かれる方が、私の弾くのを見て「変わった指遣いですね、何か理由があるんですか」とおっしゃったことがあって「実は〜」とお話ししましたが。

袴田恵子リサイタルでの歌曲伴奏(浜松アクトシティ)
2年間の休職ののち、私は、元の工場の研究所に戻りました。本社での事務仕事より、まだ工場の方がいいかと、人事部の温情もありました。また、フルコンが弾ける生活が始まったんです。
―そうでしたか。
お客様相談窓口では、きちんとお客様の質問や苦情に対応できるよう、業界の歴史、会社の歴史を勉強して調べ始めたら、だんだんと楽しくなってきて、休みの日も図書館で調べ物をしたりするようになり、ピアノ産業を研究されている先生方との交流も生まれました。エンドユーザーとの真剣勝負、やっている時は大変ですけれど「本当に勉強させてもらったな」と、あの窓口の日々もそういうふうに思います。
―10月にシゲルカワイSK-5をご自宅に入れられていかがですか?選ばれた時の決め手は?
もうすぐ私も定年ですし、会社に恩返ししたい、という思いもありました。また、選ぶに当たっては、弱い音が綺麗な音で出て欲しいということがありました。
―それでは、三浦さん、何か一曲、お聞かせいただけますか?
はい、ではオペラ《蝶々夫人》の通称「ハミング・コーラス」のところを。蝶々さんが、ピンカートンの帰国を待って3年、ピンカートンが乗っているであろう船が入港してきたという長崎港を見下ろすところで夜明け待つ場面に流れる曲です。コーラスがバックでハミングだけで歌う静かな曲ですが、夜明けを表現しています。それをピアノでうまく表現できたら、といつも思っています。(演奏くださる)
―本当に、ピアノの澄んだ響きを大切に弾いていらっしゃるのが伝わってきます。
―本日は、素敵なお話と演奏をお聞かせくださいまして、ありがとうございました。
(聞き手・安永愛)

